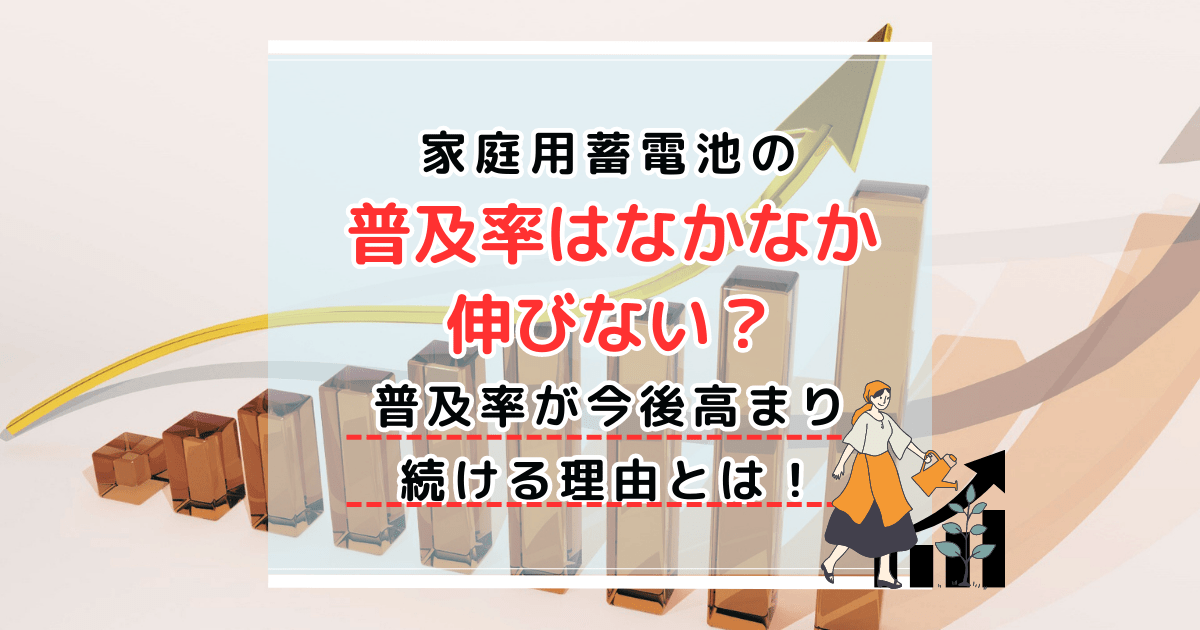蓄電池は災害時の備えや電気代節約などにおいて非常に活躍してくれるシステムです。
しかし、一家に一台蓄電池といえるほど、家庭用蓄電池の普及率は劇的に進んでいません。今回は家庭用蓄電池の普及率について解説します。
家庭用蓄電池の普及率が一家に一台といえるまで伸びない理由
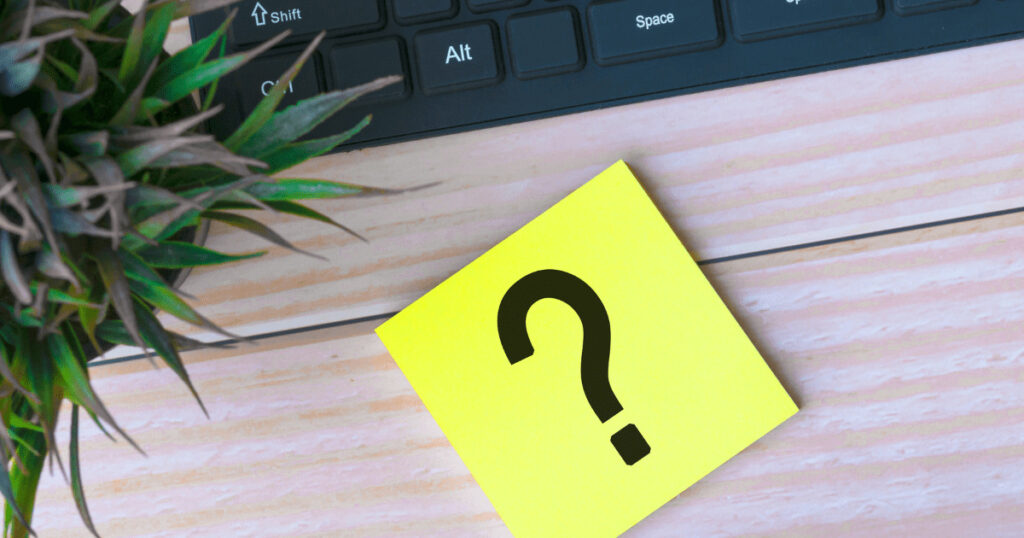
家庭用蓄電池は非常に役立つシステムです。未だに一家に一台といえるまで普及率がなかなか進んでいないのは何故でしょうか。考えられる理由は以下のとおりです。
導入費用が高額
1つ目は「導入費用が高額」だからです。
家庭用蓄電池の設置費用相場は、本体代と工事費込みで約100〜200万円とされており、まとまった初期費用の用意を考えると、導入を踏みとどまってしまうのではないでしょうか。
一般的に蓄電池の寿命目安は10〜15年くらいであり、長期運用が前提となるので故障のリスクにも備えなければいけません。
また、耐用年数まで故障がなかったとしても、家庭用蓄電池への初期費用を償却できない可能性もあります。何故なら、初期費用回収が可能かどうかは、家族構成やライフスタイル、システムによる発電量や屋根の形、方角など様々な要因が絡んでいるからです。
電気代の節約や売電収入を考えるとプラスになりますが、初期費用回収が可能かどうかの不安などが家庭用蓄電池の普及を妨げる要因といえるでしょう。
売買単価の下落し続けている
2つ目は「売買単価の下落し続けている」からです。
住宅用太陽光発電の余剰電力の買い取り期間は、FIT制度により固定価格で10年間と定められています。たとえば、2009年11月に適用された場合、2019年11月以降に買い取り期間を順次満了することになります。満了した方のことを卒FITといいます。
FIT制度開始時は買取価格が48円だったのに対して、売電単価は年々下落しており、2023年度の太陽光発電のFIT売電価格は、容量が10kW未満で16円/kWhであり、一般的な家庭が電力会社から購入している電気代単価を下回っているようです。
参照:資源エネルギー庁「太陽光発電について」(chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/pdf/082_01_00.pdf)
卒FIT後も電力会社を選んで売電はできますが、買取相場は1kWhあたり7〜9円ほどと大幅に安くなります。新電力会社の中には高額で買い取ってくれる事業者もいますが、それでもFIT価格より安いです。
そのため、家庭用蓄電池で貯めた電力を売電することで初期費用を回収することが難しくなっており、普及を踏みとどまる方も多いのかもしれません。
設置場所の確保が難しい
3つ目は「設置場所の確保が難しい」からです。
家庭用蓄電池は容量が大きいほどサイズが大きくなり、設置場所を確保しておかなければいけません。
最近では壁掛けタイプや高性能かつコンパクトな家庭用蓄電池も登場してきていますが、置く場所がないと蓄電池導入に踏み切れない方も多いようです。
蓄電池の出荷台数は年々増えている(蓄電池の価格は年々下がってきている)

様々なデメリットから、家庭用蓄電池の普及率は一家に一台とまではいっていませんが、蓄電池の出荷台数は年々増えてきています。
JEMA蓄電システム業務専門委員会で行ったJEMA蓄電システム自主統計出荷実績から、国内の蓄電システム市場の出荷台数と容量は、以下のように年々増加していることがわかっています。
| 年度 | 出荷台数と容量 |
| 2015年度 | 約3.7万台(30.8万kWh) |
| 2016年度 | 約3.4万台(23.6万kWh) |
| 2017年度 | 約4.9万台(31.1万kWh) |
| 2018年度 | 約7.3万台(49.4万kWh) |
| 2019年度 | 約11.5万台(81.4万kWh) |
| 2020年度 | 約12.7万台(88.5万kWh) |
| 2021年度 | 約13.4万台(97.2万kWh) |
| 2022年度 | 約14.3万台(109.4万kWh) |
(chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.jema-net.or.jp/Japanese/data/jisyu/pdf/libsystem_2022.pdf)
(chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2022FY/000050.pdf)
家庭用蓄電池導入実績が伸びつつある理由は、家庭用蓄電池普及開始時よりも工事費を除く蓄電池システムの総額水準が下がりつつあるからです。
参照元:三菱総合研究所「定置用蓄電システムの普及拡大策の検討に向けた調査」
(chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2022FY/000050.pdf)
2015年度と2022年度を比べると、10.4万円/kWhも安くなっています。蓄電池システムの価格水準が下がったことは、家庭用蓄電池普及率が高まりつつある理由の一つといえるでしょう。
蓄電池の普及率が高まる可能性がある理由

国内の蓄電システム市場の出荷台数と容量は増加傾向にあり、普及率も高まり続けると予測されています。その理由は以下のとおりです。
防災対策への関心が高まった
1つ目は「防災対策への関心が高まった」からです。
日本は地震や台風・洪水などといった自然災害が多い国です。2011年の東日本大震災をはじめ、大規模な災害が近年増えたことにより、防災対策への関心が高まっています。
電化製品が溢れている現代において、災害時に長期間の停電が発生した場合、電気のある生活と同じように過ごすことは厳しいです。
日常で電気が使えないとなると、暑い夏や寒い冬の場合空調が止まってしまうため体調を崩したり、生命の危機に陥る可能性もあります。
家庭用蓄電池を導入していれば、長期間の停電が発生したとしてもエアコンや冷蔵庫などを使用することが可能です。災害時に命を守る対策として、家庭用蓄電池導入の授業は今後ますます高まるでしょう。
電気自動車普及率が高まりつつある
2つ目は「電気自動車普及率が高まりつつある」からです。
電気自動車と蓄電池の併用には、経済的に以下のような大きなメリットがあります。
- 充電スポットに行かなくても蓄電池を使って自宅で充電できる
- 夜間に蓄電池に貯めておいた電気を電気自動車に充電させることで、燃料費を大幅に抑える
- 災害などで長期停電が続いた場合、電気自動車を蓄電池代わりに利用できる など
また、自動車メーカーから販売されている電気自動車の種類も年々増えつつあります。経済産業省と環境省は、補助金を用意して電気自動車の普及を促しており、今後も電気自動車の普及率は高まるのではと考えられています。
このような理由から、電気自動車の普及が蓄電池普及率を向上させるのではないかと考えられています。
売電ではなく自家発電自家消費がお得になった
3つ目は「売電ではなく自家発電自家消費がお得になった」からです。
卒FIT後も電力会社に売電することは可能ですが、FIT制度適応中のような固定価格での売電収入は得ることができません。
安い売電価格で売電するよりも、蓄電池をうまく使って高騰し続ける電気代を節約するほうが非常にお得です。
夜間電力✕蓄電池の組み合わせは光熱費節約に強いですが、そこに太陽光発電が加わると自家発電自家消費が可能となるので、電気代をかなり節約することが可能です。
下記記事で、家庭用蓄電池と節約について詳しく解説していますので、あわせてお読みください。
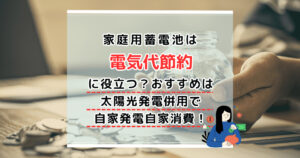
低い売電価格で売電収入を得るよりも、家庭用蓄電池を導入して電気代節約に切り替える方がお得になったことは、一般家庭で蓄電池を導入しようと普及が伸びている要因の一つといえるでしょう。
蓄電池の補助金が充実している
4つ目は「蓄電池の補助金が充実している」からです。
国や都道府県・市町村などの地方自治体から条件を満たした場合、家庭用蓄電池導入時に補助金を受け取ることができます。
都道府県と市町村の補助金が他の補助金と併用可能な場合、最大で3箇所から補助金を受け取ることが可能です。
2022年度の東京における補助金は、1kWhにつき10万円、最大80万円という高額の補助金が出ました。2023年度ではさらに増額され、1kWhあたり15万円、最大120万円です。
2023年(令和5年)東京都の太陽光発電・蓄電池補助金の申請期間は、2023年5月29日からです。予算がなくなったら締め切られてしまうため、早いうちに検討を進めておきましょう。
初期費用の高さが導入を踏みとどまらせていた場合、補助金の充実は家庭用蓄電池普及率増加の心強い味方といえるでしょう。
まとめ

家庭用蓄電池と普及率について解説してきました。以下まとめになります。
- 家庭用蓄電池は初期費用が高く、設置場所確保が難しいので一家に一台あるほど普及率が伸びない
- 工事費を除く家庭用蓄電池システム価格水準は年々下がり、国内出荷台数も年々増加している
- 災害対策の高まりや自家消費による電気代節約、補助金の充実性などにより、家庭用蓄電池の普及率は今後も伸び続けるといえる
家庭用蓄電池は年々価格水準が下がってきていますが、それでもまだ気軽に購入できる金額ではありません。しかし、高騰し続ける電気代節約や災害対策などを考えると、今後家庭用蓄電池の普及率は徐々に伸びていくでしょう。
2023年は補助金が充実しているので、太陽光発電をすでに家庭に導入している方はこれを機に蓄電池導入を検討してみてはいかがでしょうか。